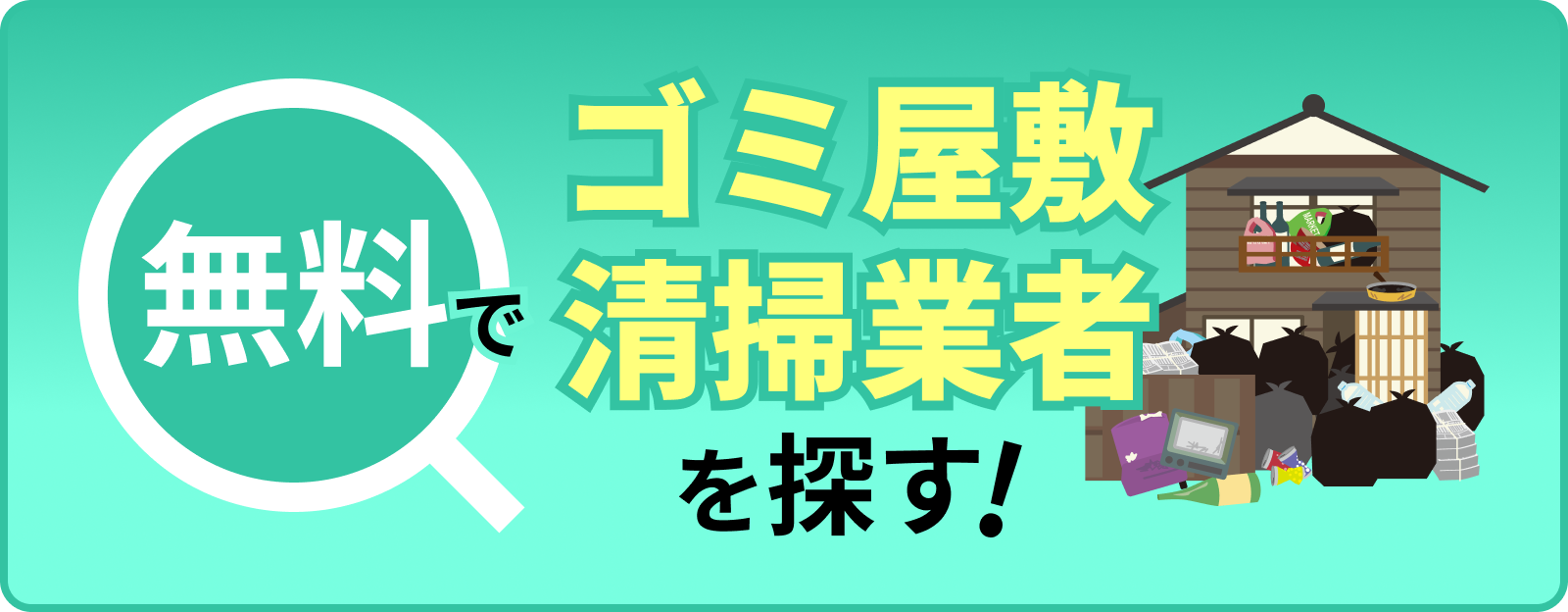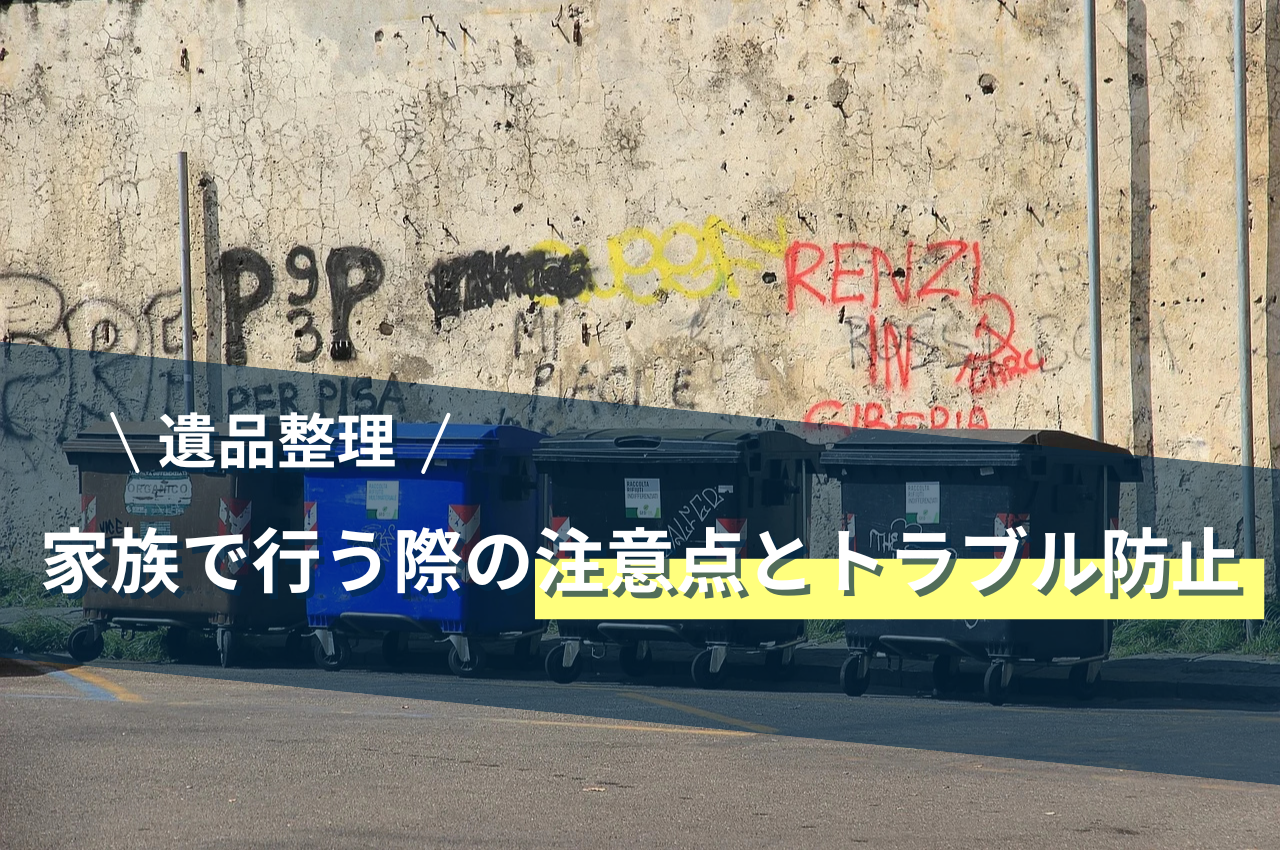遺品整理のプロセスと適切なタイミング
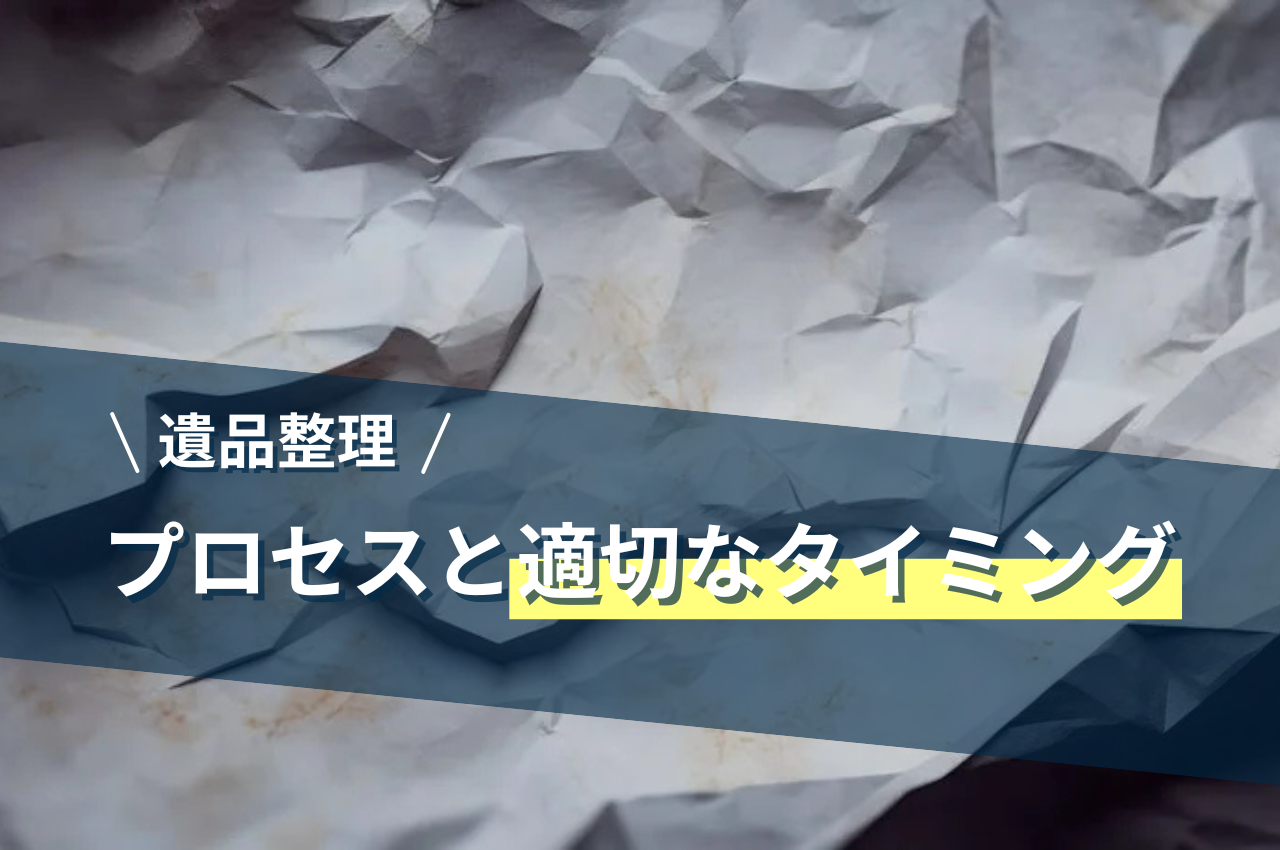
「遺品整理のタイミングっていつまでにするべきなの?」
そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
大切な家族が亡くなり葬儀で追われているなか、遺品整理の問題も出てきていつ始めるべきか迷っている人も多いと思います。遺品整理は、基本的には気持ちの整理がついたタイミングに行うものですが、故人の状況や相続人との兼ね合いによって、一定の時期までに終わらせる必要も出てきます。
遺品整理のプロセスと適切なタイミングを詳しく見ていきましょう。
遺品整理の適切なタイミングはいつ?

冒頭でも説明した通り、遺品整理のタイミングは自分で決められます。
とはいえ”いつ頃までに遺品整理を終えるか”は適切なタイミングも存在します。
具体的にいつまでに遺品整理を終えるべきなのか、タイミングについて詳しく見ていきましょう。
葬儀直後(1週間以内)
葬儀直後に、遺品整理を行うケースも多く見られます。葬儀で相続人が集まっていることもあり、遺品整理について相談しやすいのも理由の一つです。遠方に住んでいる相続人が多いときは葬儀直後のほうがスムーズに進められると思います。また、孤独死のように事情がある場合にも、葬儀直後に遺品整理を行うケースが多く見られます。ただし、葬儀直後は精神的な負担が大きくなるため、遺品整理が難しい人もいると思います。必ずしも葬儀直後に行うべきものではないので、精神的な疲労が解消されてから遺品整理を始めてみてもいいでしょう。
諸手続きを終えてから(月末)
役所関係の手続きを終えたあと、1か月程度してから始めるケースもあります。葬儀もひと段落しますし、手続きも落ち着いてくると作業にとりかかりやすい時期とも言えます。また、故人が賃貸に住んでいた場合や、退去日が決まっているときは、次に家賃が発生する前に遺品整理を終え引き渡しができるように片付ける必要が出てきます。いつまでに片付けるべきかは、大家さんや管理会社に相談しておくと、適切なタイミングを教えてもらえます。気持ちの整理がついていない人の場合、急ぎで片づけるべきとはいえませんが、書類整理などのできる範囲から行うようにしていきましょう。
四十九日の法要が終わったあと
四十九日の法要は、故人が安らかに成仏するタイミングです。どのタイミングに遺品整理を行うべきか迷っているご家族の場合、四十九日の法要が終わったあとに行われるのが一般的です。法要で親族が集まるタイミングでもあるので、遺品を形見分けしやすいのも理由と言えるでしょう。葬儀や法事なども落ち着きますし、精神的にも少しずつ余裕が出てきます。遺品整理を進められない人にとっても、一つの気持ちの区切りがつけやすいのも四十九日の法要後と言えるでしょう。
気持が落ち着いたタイミングで行う人もいる
遺品整理は、必ずしもこの日までに行うべきという決まりがないからこそ自分の気持ちを尊重してみてもいいと思います。自分の気持ちが落ち着き、遺品整理に対して前向きになったタイミングで少しずつ片付けていくのをおすすめします。精神的な負担が大きい時期でもあるので、焦らずに自分なりのペースを大切にするようにしてください。なかには、遺品整理が思うように進まず、亡くなってから半年以上かかって片付ける人もいます。個人差があることなので、あくまでも一つの基準としてタイミングを考えるようにしましょう。
遺品整理をいつ行うか決める時のポイント

遺品整理を始めるタイミングについては、悩むポイントです。
具体的には以下のポイントを踏まえて決めるようにしていきましょう。
・自分で片づけるか業者に依頼するかで決める
・作業ができる人を確保できるかで決める
・相続の手続きに間に合うかで決める
・遺品の量やごみの処理日で決める
遺品整理をいつ始めるか決めるうえで、考慮するポイントを詳しく解説します。
自分で片づけるか業者に依頼するかで決める
遺品整理を自分で片づけるか業者に依頼するのかによっても、スケジュールは大きく変わってきます。例えば、自分で片付けを行う場合、時間や労力を考えると日程に余裕を持たせて進める必要があります。自治体のごみの回収に間に合うように片づけたり、回収日当日に持っていく手間も含め考えなくてはいけません。業者に依頼する場合は、プロが効率を重視して進めてくれるので手間のかかる作業もあっという間に終わります。遠方に住んでいて何度も通うのが難しい場合や、不用品を処分できない人は業者に依頼してしまったほうが安心です。業者に依頼する場合は、予約できるタイミングに合わせてスケジュールを調整する必要が出てきます。
作業ができる人を確保できるかで決める
遺品整理は、一人で行うのか家族や親戚と一緒に行うのかによってスケジュールも変わってきます。共働きも増えているため、土日など限られた曜日しか遺品整理ができないケースもあるでしょう。作業してくれる人数が多いほどスムーズに進むため、できるだけ多くの人が集まるタイミングで片付けが進められるようにしてください。遺品整理は精神的な負担も大きくなります。自分だけだと、片づけるタイミングがわからない人にとって、他に作業をしてくれる人のスケジュールも含め決めたほうが、精神的な支えにもなります。
相続の手続きに間に合うかで決める
相続などの手続きに間に合うタイミングかどうかで、遺品整理のスケジュールを決める方法もあります。例えば、法属放棄や限定承認の申述は、死亡したことを知った日の翌日から3か月以内と決められています。手続きを行う為には、家庭裁判所に必要書類をそろえ提出(郵送でも可)しなくてはいけません。遺品整理で故人の借金が見つかった場合、相続放棄を考えるケースもあるでしょう。
他にも、被相続人が亡くなった年の所得税の申告は、死亡したことを知った日の翌日から4か月以内と決められています。税金の申告期限や法律の期限が決まっている場合は、遺品整理のスケジュールを逆算しつつ決めることをおすすめします。計画的に進めていかないと必要な手続きができなくなってしまいます。
遺品の量やごみの処理日で決める
遺品整理といっても、処分するごみの量はそれぞれ違います。そのため、大量の遺品がある場合や、家具家電のように粗大ごみが多い場合は計画的に進めていく必要があります。自治体によってごみの回収日が決まっているため、いつでも処分できるわけではありません。遺品の全体量を把握することはもちろん、作業時間がどの程度かかるのか見積もりをとることから始めてみてください。ごみの処分ができるスケジュールに合わせて、遺品整理を進めていくことをおすすめします。
遺品整理で覚えておきたいプロセス

遺品整理の手順について、誰かが教えてくれるわけではありません。
状況も違えば、手続きの多さや遺品整理の大変さも変わってきます。
あくまでも一般的な指標にはなりますが、遺品整理で覚えておくべきプロセスを紹介します。
1.必要な手続きや書類集めを進めておく
2.片付けのスケジュールを決め気持ちの整理をする
3.相続人のスケジュールを合わせ整理をする
4.迷ったときはボックスにまとめておく
5.関係者関連がわかる手帳などは残しておく
6.必要な書類は写真も一緒に残しておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.必要な手続きや書類集めを進めておく
亡くなってすぐにやらなくてはいけないことは、税金や契約書類の確認です。
期日が決められているものも多いため、まずは把握したうえで手続きを進めていきます。
具体的には以下のような手続きが出てきます。
☑法務局に死亡届の提出(葬儀会社が行ってくれる場合もある)
☑銀行口座の解約手続き(親族の承認必須)
☑生命保険の解約手続き
☑電気ガス水道などの解約手続き
☑携帯電話の解約手続き
☑マンションの解約手続き(賃貸に住んでいた場合)
手続きによって、書類がないと進められないものもあります。
税金の手続きなど役所関係は直接行って手続きを行うものもあるため、早めに進めましょう。
2.片付けのスケジュールを決め気持ちの整理をする
大切な家族を亡くした喪失感はすぐに解消できるものではありません。遺品整理など何もやる気が起きずに、辛い思いをしている人もいるでしょう。遺品のなかには、故人との思い出が詰まっているものも多くありますし、向き合いながら片づけなくてはいけなくなります。まずは、自分の気持ちを整理することから始めるようにしていきましょう。時間が解決してくれることもあると思います。
3.相続人のスケジュールを合わせ整理をする
遺品整理を複数人で行う場合、片付けのスケジュールを決めなくてはいけません。誰がどこを片づけるのかを相談して決めておかないと、片付けがスムーズに進まなくなってしまいます。不用品の処分についても、自治体に依頼するのか、不用品回収業者を呼ぶのかなど細かな部分まで決めておきましょう。当日に決めようとしても話し合いがまとまらなくなってしまい、思うように片付けが進まなくなってしまうこともあるでしょう。効率的に進めるためにも、事前に決めておくことが大切です。
4.迷ったときはボックスにまとめておく
遺品整理をしていると、処分に困るものも出てきます。都度、確認していては片付けも進まなくなってしまうため、迷ったときは1つのボックスにまとめられるようにしておきます。まずは、片付けに集中できるようにしておき、ボックスのなかにあるものは後から見直せるようにしておきましょう。同時に進めていくのではなく、まず、優先するべきことを決めて進めていくのがポイントです。
5.関係者関連がわかる手帳などは残しておく
故人の持っていた手帳など、関係者関連のわかるものはすぐに処分しないようにしましょう。思い出がたくさん詰まっているものになりますし、周囲の人間関係を把握するきっかけにもなります。また、葬儀に呼べていない人でも亡くなったことを知ればお線香を希望する人もいます。関係者関連がわかるようにするためにも、手帳など一時的に残しておくことをおすすめします。
6.必要な書類は写真も一緒に残しておく
遺品整理で出てきた書類や遺言、家系図など紛失すると困るものは写真に撮って残しておきます。原本は時間とともに劣化していきますが、スキャンなどデータ化を進めておけば必要なときに印刷して使えます。遺品整理のときや財産分与で使う可能性もあるため、書類をそのままにせず、写真やスキャンで残しておくように習慣づけておきましょう。
遺品整理のタイミングが遅くなるとおきるトラブル

遺品整理が思うように進まない…なんて話も珍しくありません。
特に親が亡くなるなど親しい間柄の人が亡くなった場合、悲しみが大きくなってしまい遺品整理ができなくなってしまいます。その場合、無理をせずにまずは自分の気持ちを整理する時間を十分にとるようにしましょう。ただし、遺品整理のタイミングが遅くなると起きるトラブルも考えられます。
・親族が勝手に片付けたり処分する可能性もある
・相続税のかかる遺品は10か月以内に申請する必要がある
・遺産相続放棄の手続きが出来なくなる
・生前に契約していたサービスの請求が続いてしまう可能性がある
・賃貸などすぐに解約しなくてはいけない場合もある
・余計に気持ちの整理がつかなくなることもある
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
親族が勝手に片付けたり処分する可能性もある
遺品整理を後回しにしていたら、親族が勝手に処分してしまった…なんて話も珍しくありません。本来であれば、相続人同士で話し合いをしたうえで処分するべきなのですが、勝手にもって帰ってしまうなどのトラブルが起きてしまうこともあります。こうしたトラブルを避けるためにも、早めに話し合いをして決めておきましょう。
相続税のかかる遺品は10か月以内に申請する必要がある
故人の遺品のなかに、5万円を超える動産があるときは「課税対象」とみなされ、相続税の申告が必要になります。相続税は、死亡したことを知った日の翌日から10か月内に行うように決められています。3000万円以上の相続財産がある場合、遺品整理や形見分けを早めに済ませておくことが大切です。遺品整理が遅れてしまうと、何度も申告のやり直しになってしまったり、期日までに間に合わなくなってしまうこともあります。後々のトラブルを避けるためにも、すべての遺産を明確にしておき計画的な遺品整理が進められるようにしていきましょう。
遺産相続放棄の手続きが出来なくなる
故人の遺産のなかには、借金などの負の遺産が含まれている可能性もあります。借金のほうが多く相続しない選択をする人もいます。その場合、家庭裁判所にて遺産相続放棄の手続きを行わなくてはいけなくなります。相続放棄には「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「戸籍謄本」「収入印紙」「切手」などの必要書類を用意しなくてはいけません。相続放棄一つにしてもそろえる書類が多く、間に合わなくなってしまう可能性も考えられます。
生前に契約していたサービスの請求が続いてしまう可能性がある
故人が生前に契約していた有料サービスなど、解約しないとそのまま相続人に引き継がれるようになってしまいます。有料の月額サービスなど、何も言及がないものも多く契約を把握できずに未払い分を請求されてしまうケースもあります。不要なサービスを早めに見直しておき、すぐに解約できるようにしておきましょう。契約書類の細かな部分にまで目を通しておき、いつまでに手続きをしたらいいのか確認しておくことが重要です。
賃貸などすぐに解約しなくてはいけない場合もある
故人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理が遅くなってしまうと賃料を余計に支払う必要が出てきます。契約更新のタイミングなどもあるので、マンションやアパートなどの賃貸の場合は、早めに契約の内容を見直すようにしておきましょう。他に自宅や土地をもっていた場合、固定資産税が発生し続けるため早めに整理したうえで売却や賃貸などの対応を進めていけるようにしましょう。
余計に気持ちの整理がつかなくなることもある
遺品整理を後回しにしていると、余計に気持ちの整理がつかなくなってしまうこともあります。故人との思い出の詰まった品を目の前にすることで、整理をするのが難しくなってしまいます。すぐに片付けるべきとはいいませんが、少しずつ別れを受け入れていき気持ちを整理することも必要です。前向きな気持ちになれるように、感情の整理も進めていきましょう。
まとめ
遺品整理のタイミングは、明確にいつまでと期限が決まっている訳ではありません。ただし、遺品をそのままにしておくことで税金や手続きの制限がでてきてしまったり、金銭的な負担や感情の整理が難しくなってしまうこともあります。いつまでに片付けるのかを決めるためにも、遺品の量や種類、自治体ごとによって変わるゴミの回収日も含め、相続人同士で話し合い早めに決めておきましょう。
この記事の監修者:編集部:三島

遺品整理のプロが運営するこのサイトでは、片付けのコツや裏話、失敗しないためのテクニックなど、役立つ情報が満載。読んで楽しみながら、実際に使える知識が手に入ります。 コラムも順次、更新予定なので、お楽しみに!ゴミ屋敷からおさらばしたいならご一読ください!