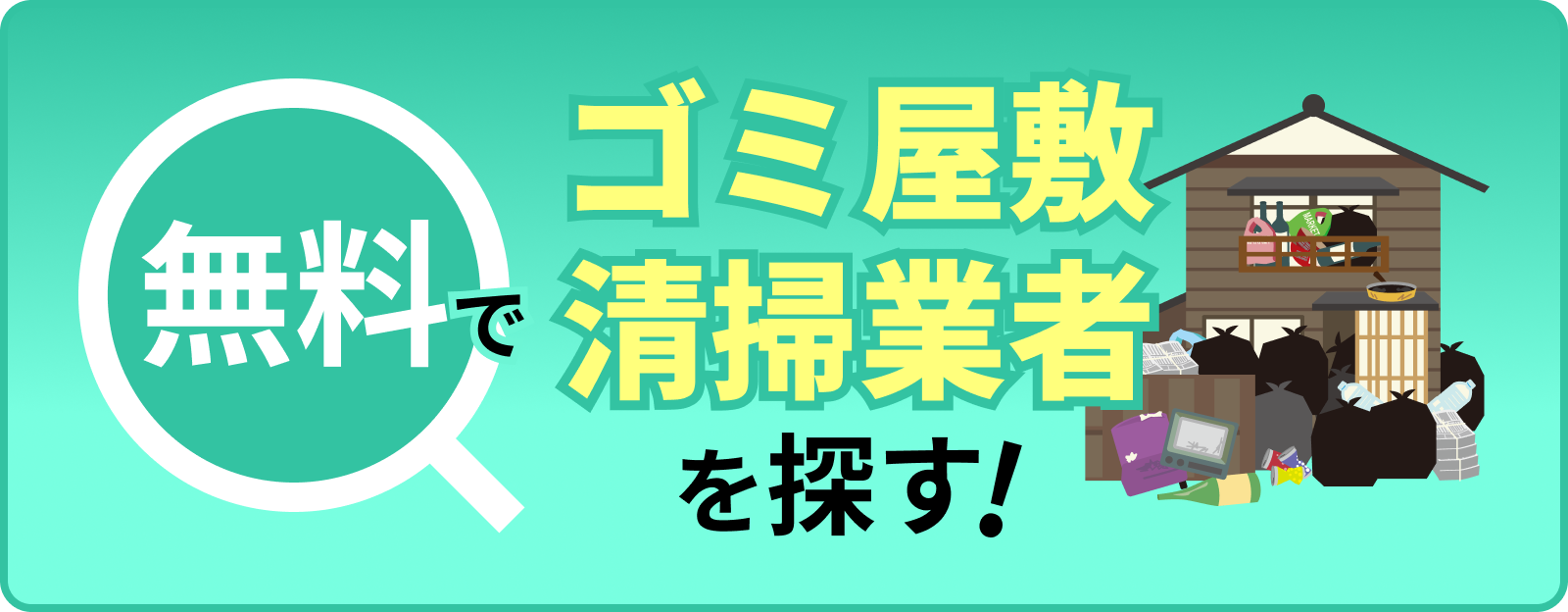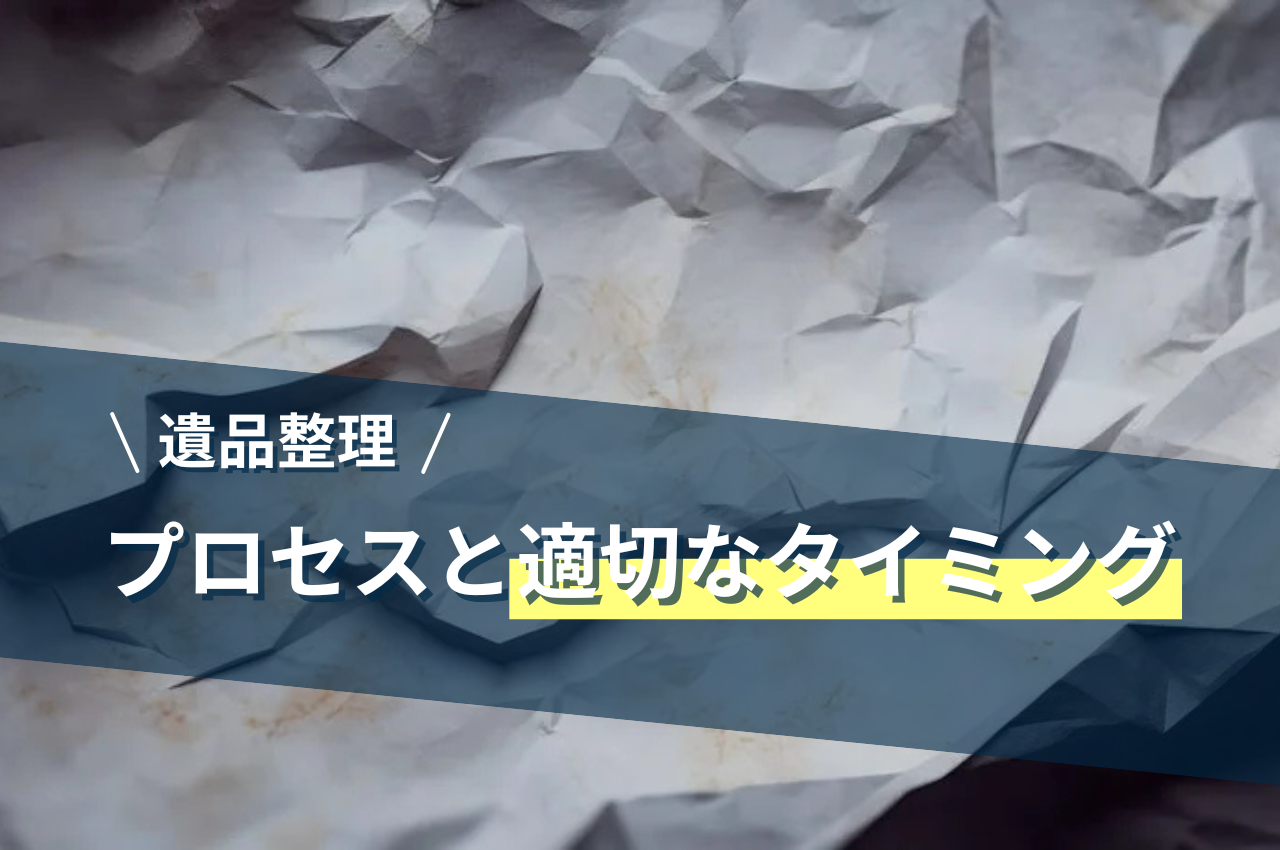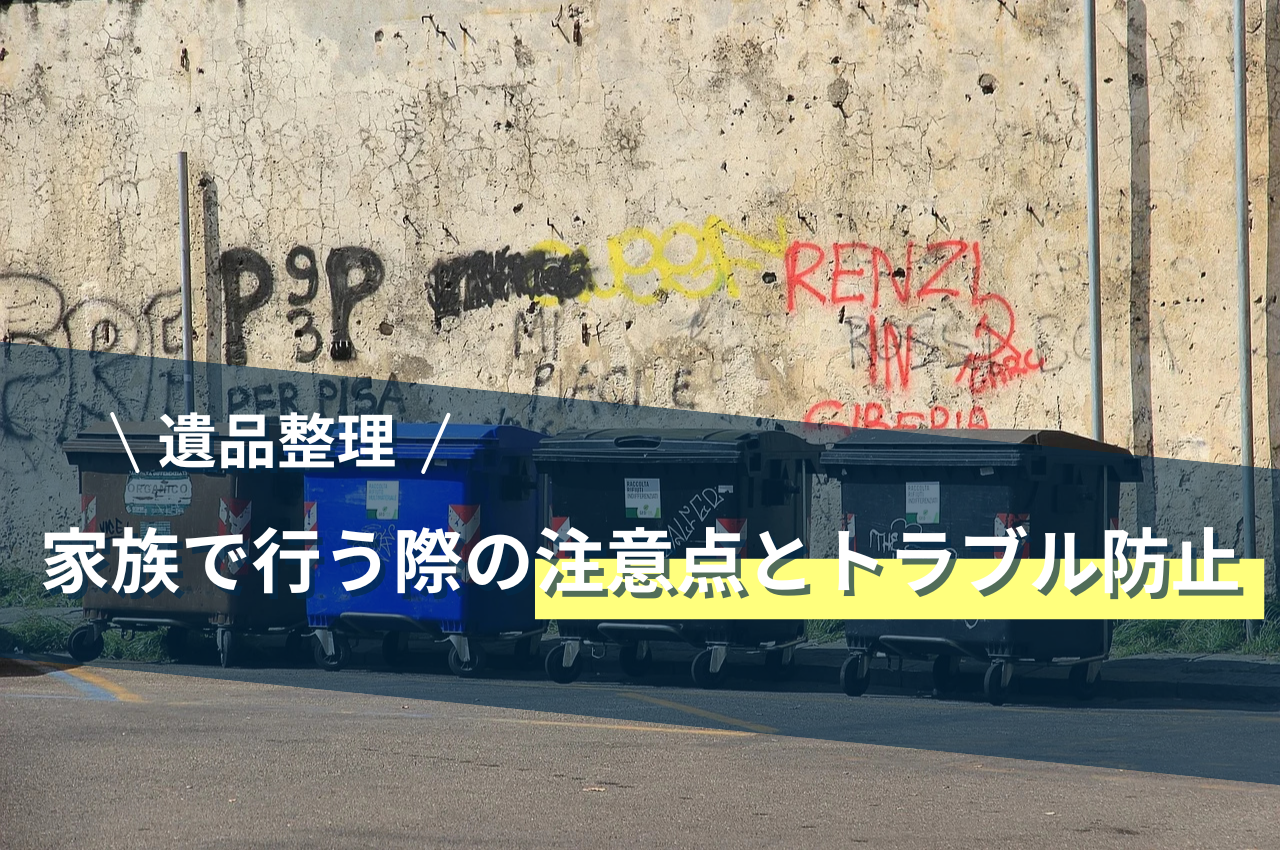遺品整理が必要なタイミングとその心理的負担を軽減する方法

遺品整理をいつ行うべきか、タイミングで迷っている人もいるのではないでしょうか。
遺品整理は行わなくてはいけないものではありますが、必要な時期やタイミングはそれぞれの事情によっても異なります。遺産整理における心理的負担を軽減するためにはどうしたらいいか、そのためのポイントも含め解説します。遺産整理について、前向きな気持ちになれずに悩んでいる人も参考にしてみてください。
遺品整理が必要な時期はいつ?タイミングを紹介

遺品整理が必要な時期は、個人差があります。
どのタイミングで行うべきか迷っている人向けに、状況別に詳しく解説していきます。
・賃貸契約がある場合は早めに片づける(7日後~)
・施設に入所していた場合も期限を確認する(7日後~)
・役所関係の手続きが終わりひと段落ついた時期(14日後~)
・四十九日の法要に合わせて片付けを行う(49日後~)
・相続税の申告期限である10か月内
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
賃貸契約がある場合は早めに片づける(7日後~)
故人が賃貸マンションやアパートに住んでいた場合は、早めの遺産整理が必要になってきます。葬儀や告別式が終わり、亡くなってから7日以内に「死亡届」を提出します。死亡直後の手続きが終わったタイミングで遺品整理を行います。
賃貸契約は死亡した後も継続し、毎月の賃料がかかります。契約更新のタイミングもあるため、どのような契約状況になっているのかを確認したうえで、早めに遺品整理を行うようにしましょう。遺品整理をして原状回復費用を支払ったあと、正式に契約を解約する流れになります。
施設に入所していた場合も期限を確認する(7日後~)
故人が老人ホームなどの施設に入っていた場合も、7日前後で片付けるようになります。施設によっても対応が変わってきますが、次の入居者の兼ね合いもあるため1習慣以内の対処を定めているところもあります。知らずに片付けを後回しにしてしまうと、施設に迷惑をかけてしまうことも考えられます。
前もって施設にルールを確認しておき、いつまでに退去するべきかを確認しスケジュールを考えるようにしておきましょう。急ぎで片付ける場合は葬儀が終わってすぐに、遺品整理を始めるのをおすすめします。
役所関係の手続きが終わりひと段落ついた時期(14日後~)
賃貸や施設に入居していない故人であれば、亡くなって14日前後に遺品整理を行うこともあります。亡くなった後に期限が決められているものに「社会保険」と「国民年金(厚生年金)」の手続きがあります。
故人の住所のあった役所にて「資格喪失届」を提出したうえで、故人の保険証を返却します。年金は年金事務所にて受給停止の手続きを行うことになります。厚生年金は10日以内、その他は14日以内に手続きをしなくてはいけません。
役所関係の手続きが終わってから、遺品整理を行うケースもあります。
四十九日の法要に合わせて片付けを行う(49日後~)
故人が亡くなって四十九日目に行われるのが「四十九日」に合わせた法要です。仏教では、四十九日までは現世をさまよっていると考えられ、一区切りとして遺品性入りを行う人も少なくありません。
徐々に気持ちに余裕ができてくるタイミングでもありますし、法要で親族が集まるため形見分けの機会としても最適です。お互いに納得して遺品整理を進められますし、話し合いの機会にもなります。ある程度希望を伝えられるように意見をまとめておくと、遺品整理もスムーズに進めやすくなります。
相続税の申告期限である10か月内
故人の遺産が多く非課税枠を超えているときは「相続税」の支払が必要になります。そのため、相続税の申告や納税を行わなくてはならず、亡くなってから10か月の間に行うことになります。相続税を出すためには、遺品整理を行わないと何があるのかわかりません。
故人の遺品を明確にしたうえで、遺産の評価総額を把握することからはじめていきましょう。遺産のなかでも通帳や保険などの金銭的なものから土地や建物などの不動産、貴金属など査定を必要とするものもあります。
すべてを把握するのは手間もかかるため、早めに行動するようにしておきましょう。
ちなみに遺産を相続しない「相続放棄」の場合は、亡くなってから3か月以内に手続きを行う必要が出てきます。手続きをしないと「単純承認(すべてを相続)」としてみなされてしまいます。「限定承認(一部のみ相続)」を希望する場合も期限に気を付けましょう。
遺品整理は気持ちが落ち着いてから行う人もいる

遺品整理は、必ずしも決められた期日があるわけではありません。一人で抱え込むのは逆効果になるため、おすすめできません。
故人の状況によっては、気持ちが落ち着いてしっかりと向き合えるようになってから行う人もいます。それだけ遺品整理は精神的にも大きな負担がかかることでもあるのです。
・遺品整理がつらいと感じる理由は人それぞれ
・遺品整理のタイミングに決まりはない
・故人の状況によって遺品整理を行うべき
・遺品整理を無理に進めるとうつ病のリスクがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺品整理がつらいと感じる理由は人それぞれ
遺品整理は大切な人との最後のお別れでもあり、心身ともに大きな負担がかかります。悲しい気持ちもありますが、戸惑ったり、後悔するなどさまざまな感情と向き合うことになります。家族同士の意見の違いによるトラブルにも直面しているかもしれません。
遺品整理で故人を思い出し、強い喪失感が出てきてしまう人もいます。思い出の品を目にして、心が揺さぶられることもあるでしょう。また、故人のものを処分することに強い抵抗感を感じ、捨ててしまってもいいのか迷うこともあるでしょう。
また、遺品整理の進め方がよくわからず、不安になってしまい進められない人もいるかもしれません。遺品整理がつらいと感じる理由は人によって違って当たり前です。まずは自分の気持ちに対して向き合ってあげるようにしてください。
遺品整理のタイミングに決まりはない
遺品整理のタイミングが明確に決まっているわけではありません。人によっては親族が集まる四十九日法要を遺品整理のタイミングとして考える人もいるでしょう。
いつ行うべきか決められない人は、法定相続人同士で相談して決めてもいいと思います。遠方に住んでいてすぐに集まれないケースもあり、できるだけ早いタイミングで…と意見が食い違ってしまうこともあるかもしれません。
タイミングは決まっていないからこそ、周りを考慮しつついつ行うべきかを決めていくようにしましょう。
故人の状況によって遺品整理を行うべき
遺品整理のタイミングは、故人の状況によっても大きく変わります。前述でも説明した通り、賃貸や施設に入居しているときは思っているよりも早めに片付けなくてはいけなくなります。一般的な目安としては、亡くなった日の月末もしくは翌月末までには行う人が多くなります。
そのまま放置していると相続税の高額請求のリスクも出てきますし、親族が勝手に遺品を処分してしまうことも考えられます。故人の状況はそれぞれ違うからこそ、状況に合わせて遺品整理を行うようにしていきましょう。
遺品整理を無理に進めるとうつ病のリスクがある
遺品整理は精神的な負担が大きいからこそ、うつ病のリスクも考えられます。心理的に大きな負担がかかる場合、作業に向き合えなくなってしまい前向きになれなくなってしまうことがあります。
故人との関係が深い人ほど、喪失感が強くなり心が沈む時間が長引くことも少なくありません。精神的な負担に向き合わず我慢してしまうと、うつ病のリスクを高めることにも繋がります。うつ病は精神的な部分だけでなく、全身に倦怠感を感じたり集中力が低下し、自己評価が低くなるなど日常生活に支障をきたすことになります。
少しでもおかしいなと思ったときは頼ることを大切にしてください。
遺品整理の心理的負担を減らす方法

遺品整理は心身にかかる負担が大きいからこそ、少しでも心理的な負担を減らすことが大切になってきます。減らし方には下記のような方法があります。
・処分に迷ったら無理に捨てようとしない
・遺品整理業者に依頼する
・家族や友人など頼ることも必要(複数人で作業する)
・カウンセリングを受ける方法もある
・少しずつ時間をかけて整理を進めていく
・遺族同士のコミュニケーションをとる
具体的にどのような減らし方があるのか説明します。
処分に迷ったら無理に捨てようとしない
遺品整理に迷ったときは、処分ではなくリサイクルを考えるようにしてみてください。なかには故人が大切に使ってきたものを捨てることに対して、抵抗感を持っている人もいるでしょう。
まだまだ使えるものは、リサイクルショップにて買取してもらう、寄付にだす方法もあります。遺品の出張買取を行っているお店もあるため、無理に持っていく必要もありません。処分に迷ったときは捨てる選択肢を減らし、罪悪感をなくしていきましょう。
遺品整理業者に依頼する
時間的にも遺品整理が難しい場合は、プロの遺品整理業者に依頼する方法もあります。「遺品整理士」の資格を持ったスタッフが、親族に代わって仕分けを行うことをいいます。故人や残された人の気持ちにしっかりと寄り添いつつ片付けてくれます。
遺品を大切に扱ってくれますし、適切な処分をしてくれるのも安心して利用できます。また、核家族化も進んでいるなか、一人で片付けなくてはいけない人もいるでしょう。遺品整理業者に頼りつつ、精神的な負担を減らして片付けられるようにしてください。
家族や友人など頼ることも必要(複数人で作業する)
遺品整理を一人で抱え込むのはおすすめできません。家族や友人など頼れる人に相談しつつ一緒に片付けをしてもらえるようにしておきましょう。複数人で片付けることで、話をしながら片付けたり、辛い気持ちを聴いてもらうこともできます。
遺品の量によっても変わりますが、一人で片付けるのは限界があります。頼れる存在がいるだけでも、心強く感じることもあるからこそ、複数人で作業をするのをおすすめします。
カウンセリングを受ける方法もある
遺品整理が辛いと感じてしまい、片付けに向き合えないときはカウンセリングを受ける方法もあります。故人が亡くなったあと、精神的に安定するまで待って作業を行う人もいます。また、カウンセリングも利用しつつ自分の気持ちに向き合う時間を作るようにしましょう。
「何に対して辛いと感じているのか」を話してみると、遺品整理ができない理由も見えてくると思います。客観的な意見を聞く意味でも、カウンセリングは重要です。
少しずつ時間をかけて整理を進めていく
遺品整理を一気に進めようとすると、心身に大きな負担がかかります。持ち家や施設の場合は片付けをしなくてはいけない理由もありますが、急ぎで片付けなくても良い場合は、少しずつ進めていくことも検討してみてください。
仕分けだけを行う日、不用品を処分する日と作業を分けてもいいでしょう。また、部屋ごとに片付けるタイミングを決める方法もあります。少しずつ時間をかけて整理を進めていくようにしましょう。
遺族同士のコミュニケーションをとる
関係性によっても変わりますが、遺族同士のコミュニケーションを積極的にとるようにしてください。お互いの精神的な負担の軽減にも繋がりますし、トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
話合わないままだと、いくら親族だとしてもお互いの気持ちがわからないままになってしまいます。とはいえ、親族同士で会話をするのが難しいような関係性の場合もあるでしょう。感情的になってしまうときは、一度時間を置き話すようにしましょう。
まとめ
遺品整理が必要な時期は、それぞれの状況によっても変わってきます。急ぎで片付けなくてはいけないケースもあり、精神的に大きな負担になる人もいるでしょう。故人のことを大切に思っているからこそ、遺品に向き合うというのは、思っている以上に辛いものです。
一人で抱え込むことがないように、頼れるところは相談しつつ進めていけるようにしましょう。必要な手続きもあるため、事前にスケジュールを決めつつ作業を進めていくことが大切です。
この記事の監修者:編集部:三島

遺品整理のプロが運営するこのサイトでは、片付けのコツや裏話、失敗しないためのテクニックなど、役立つ情報が満載。読んで楽しみながら、実際に使える知識が手に入ります。 コラムも順次、更新予定なので、お楽しみに!ゴミ屋敷からおさらばしたいならご一読ください!