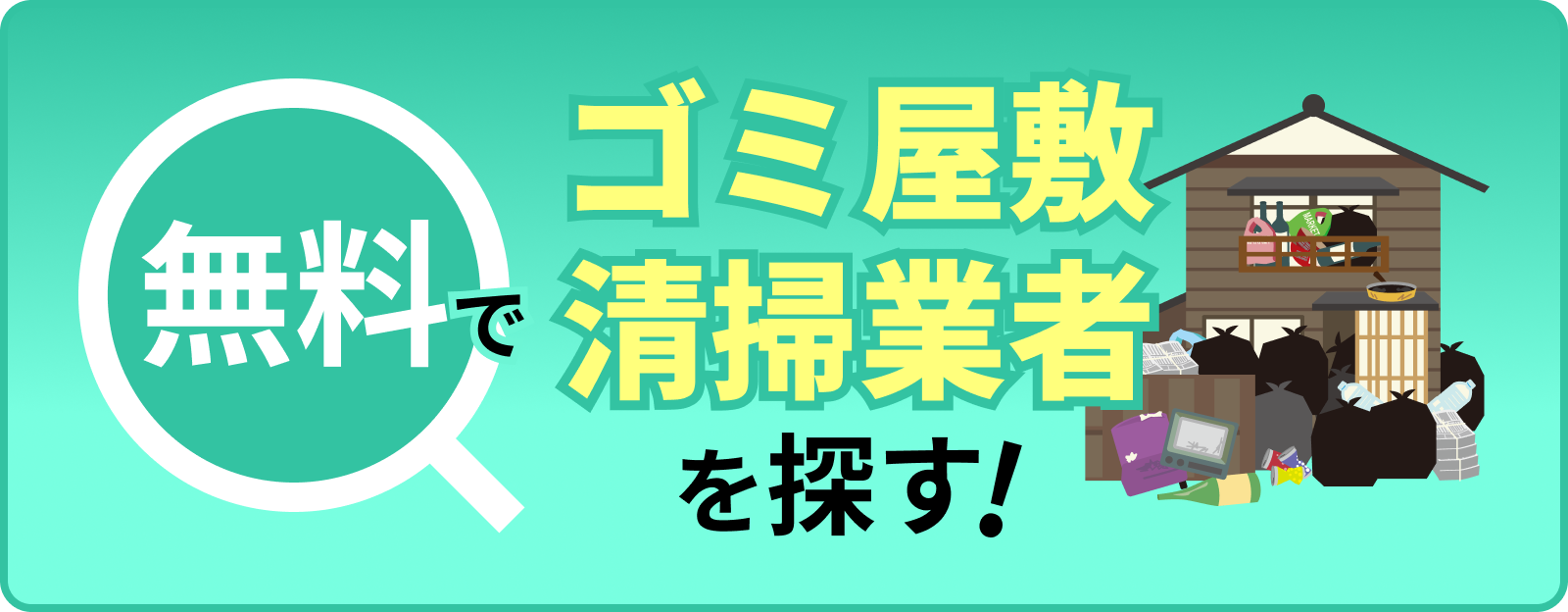ゴミ屋敷はなぜ放火されやすい?延焼の責任は誰が取るの?
投稿:
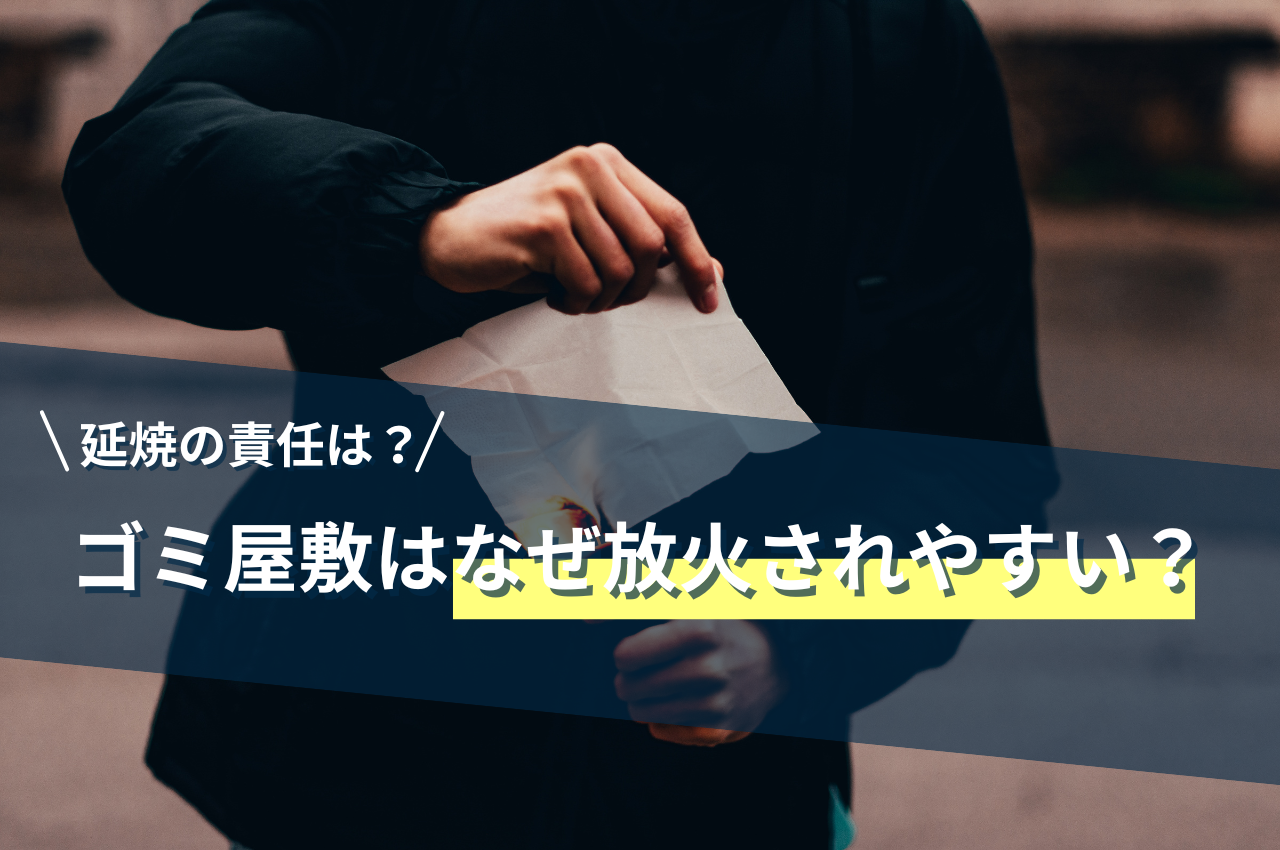
ゴミ屋敷は放火の標的になりやすく、近隣への延焼被害も深刻です。本記事では、ゴミ屋敷がなぜ放火されやすいのか、放火されないための防止策をわかりやすく解説します。
目次
ゴミ屋敷はなぜ放火されやすいの?

ゴミ屋敷は、外見的な問題だけでなく、防災の観点からも大きなリスクを抱えています。とくに放火の被害に遭いやすいと言われており、実際に火災に発展した例も少なくありません。
本記事では、ゴミ屋敷が放火されやすい3つの理由を解説します。
理由1:火が広がりやすい可燃物が多いから
ゴミ屋敷は、その場に燃えやすい物が多く放置されていることから、放火犯にとって火をつけやすい家と見なされやすいです。
放火犯がわざわざライターや着火剤を持参するとは限らず、その場で見つけた可燃物に火をつけるケースが多いのが現実です。特に、敷地まわりに段ボール、ビニール袋、衣類などが散乱していると、「ちょっとした火種」で一気に燃え広がる可能性があります。ゴミ屋敷は「その場で着火しやすい環境」が揃っており、放火のターゲットになりやすい状態にあるのです。
さらに、風通しの悪い室内や乾燥した季節では、落ちたタバコの灰、電気コードのトラブルなど、日常の小さな火種でも火災が起こりやすくなります。
このように、火事など大きなトラブルに繋がる原因は早めに解消しておくことが重要です。自力での片付けが困難な状況ではプロに頼るのも一つの方法です。気になる方はぜひこちらもチェックしてください。
ゴミ屋敷の片付けの費用相場と失敗しない業者の選び方
理由2:無人・防犯意識が低い家とみなされやすいから
放火犯は、無人に見える家や防犯対策が甘い場所を狙う傾向があります。ゴミ屋敷のように、敷地が荒れていたりゴミがあふれていると、「人が住んでいない」、「防犯意識が低そう」と見なされやすくなります。そのため、放火犯にとってゴミ屋敷は放火の格好のターゲットになりやすいと言えるでしょう。
実際、多くの放火事件は人目が少なく、侵入しやすい場所で発生しています。 こうした条件がそろっているゴミ屋敷は、放火されやすい環境が自然とできあがってしまっているのです。
理由3:死角が多く・見通しが悪いから
放火犯は「人に見られたくない」という心理が強く働いています。ゴミが家の外まであふれ、死角が多いゴミ屋敷は、彼らにとって絶好のターゲットになります。
例えば、玄関の前に大量のタイヤや古い冷蔵庫、洗濯機などの大型家電が積まれ、外から建物全体が見えにくい状態だと死角が生まれやすくなります。
さらに、廃材や粗大ごみが通路や塀の外まであふれ出している場合、敷地内に不審者が侵入しても周囲の目が届かず、気づかれにくくなります。こうした「隠れやすい」、「見つかりにくい」環境が、放火を誘発する大きな要因になっているのです。
弊社では、無料でゴミ屋敷の清掃業者をご紹介しております。お問い合わせは以下のフォームよりお気軽にどうぞ!
近所のゴミ屋敷が放火!延焼の責任は誰?

近隣にあるゴミ屋敷が放火され、その火が自分の家にまで延焼した場合、被害者としては「一体誰が責任を取ってくれるのか」と不安に感じるものです。延焼時の責任の所在については以下の3つのポイントが挙げられます。
- 放火犯が第一の加害者!
- ゴミ屋敷の所有者・居住者の責任が問われるケースもある
- 延焼してしまった近隣住民は被害者側だが、自己負担が発生するケースもある
放火は犯罪であり、本来は火をつけた本人が最も重い責任を負います。しかし、犯人が見つからない、あるいは損害賠償能力がないケースも多く、被害者が補償を受けられないまま終わってしまうことも珍しくありません。
では、火元がゴミ屋敷だった場合、住人に責任はあるのでしょうか。ここで関係するのが「失火責任法(失火法)」です。この法律では、失火による延焼でも重大な過失がなければ損害賠償責任を問われないとされています。つまり、ゴミが溢れていてもそれだけで責任を問うのは難しいということです。
ただし、可燃物を屋外に放置していた、防犯対策をまったく講じていなかったなど、火災を招きやすい環境を放置していたと見なされる場合には、管理責任を問われる可能性があります。
さらに、人命に関わる被害が出た場合は、過失致死など刑事責任に発展することもあります。
一方、失火責任法が適用されるため、延焼により自分の家が被害を受けた場合でも火元から賠償を受けることができません。したがって、もらい火による被害は、自分の加入する火災保険で対応することになります。
ゴミ屋敷は放火犯のターゲットになりやすい条件をはらんでいます。近所にゴミ屋敷がある場合は、延焼被害を想定して火災保険に加入しておくと安心です。
近所のゴミ屋敷、一体誰の責任なのか気になりませんか?以下の記事ではゴミ屋敷の責任の所在と解決方法を紹介しています。
ゴミ屋敷は誰の責任なの?解決方法は?
ゴミ屋敷が火事になった事例

ゴミ屋敷が火事になると、その被害は火元の住居だけでなく、周囲の住宅や住民にも深刻な影響を与えることがあります。
実際、総務省消防庁が発表した令和6年のデータによると、全国の火災件数のうち放火および放火の疑いによる火災は3,862件にのぼり、全体の10.4%を占めています。この統計にはゴミ屋敷に限定した件数は含まれていませんが、ゴミ屋敷には放火犯のターゲットにされやすい条件がそろっているため、放火のリスクは非常に高いと言えます。
ここでは、実際に発生したゴミ屋敷が火事になった事例を紹介しながら、そのリスクの大きさを具体的に見ていきましょう。
愛知県豊田市で3棟全半焼|過去にもボヤ騒ぎ
2015年8月25日、愛知県豊田市保見ケ丘の木造2階建てゴミ屋敷から出火し、建物は全焼。隣接する住宅2棟も全焼、半焼し、近隣に大きな被害が及びました。
出火原因は、室内で使用していた蚊取り線香が可燃物に燃え移った可能性と報じられています。 この住宅では過去にもボヤが複数回発生しており、住民から火災リスクを懸念する声が上がっていました。
この火災を受けて、豊田市は翌年の2016年に「不良な生活環境を解消するための条例」を施行。ゴミ屋敷対策条例として、指導・命令・過料といった措置が可能になったのです。
福島県郡山市でゴミ屋敷全焼|焼け跡からゴミ屋敷住人の遺体
2016年10月11日午後11時過ぎ、福島県郡山市菜根4丁目にある木造平屋建ての建物が全焼する火事が発生しました。
この建物は以前から「ゴミ屋敷」として地域で知られており、悪臭や害虫などの生活環境問題が住民の間でも懸念されていました。
市はその年の3月末、強制的に敷地内のゴミを撤去する対応(行政代執行)によって敷地内のゴミの強制撤去を実施していたものの、建物内部や全てのゴミが完全に処理されたわけではありませんでした。
火災は木造の建物全体を焼き尽くし、建物の約51平方メートルが被害を受け、焼け跡から74歳の住人男性とみられる遺体が発見されました。
この事件は、行政代執行だけでは内部のゴミや生活状況の問題を根本的には解決しきれないということを示しており、ゴミ屋敷を早期に改善することの重要性を強く感じさせる事例です。
神奈川県平塚市でゴミ屋敷が全焼|鎮火に11時間!
2020年12月3日、神奈川県平塚市の住宅密集地で火災が発生し、火元は地域でゴミ屋敷とされていた住宅でした。 70代の男性が一人で暮らしていた木造住宅には、室内外に可燃ゴミが多く堆積しており、ライターでガスコンロに火をつけようとした際にビニール袋へ引火したと見られています。
火は瞬く間に周囲に広がり、住宅や店舗など計6棟が全焼、半焼する被害が発生。消防によると、鎮火には11時間以上を要したと報告されています。
火元の住人は顔に火傷を負い、隣家の高齢女性も救出されました。大きな人的被害は免れたものの、地域全体を巻き込む深刻な火災となりました。近所に住む方のXでは、
「火事の恐ろしさを改めて認識しました。 市にずっと相談してたのに注意しか出来ないと……繰り返さない為にどうしたら……」(X投稿より/2020年12月4日)
と、語られていました。
この事例は、ゴミ屋敷で火を扱うことが重大な火災リスクにつながる現実を示しています。 可燃物が密集する中での火気使用は、いつ事故になってもおかしくありません。
近隣住民がすべきゴミ屋敷放火の3つの防止策

もし近所に放火リスクのあるゴミ屋敷があった場合、「何か起きてからでは遅い」と不安になる方も多いはずです。ここでは、近隣住民として今すぐできる防火対策を、次の3つの視点からご紹介します。
【近隣住民ができる3つの対策 】
- 自治体や消防署に相談し、行政的な支援を求める
- 警察に相談し、不審者対策としてパトロール強化を依頼する
- 自治会や町内会など地域全体で協力し、情報共有・連携を図る
まずできるのが、自治体や消防への相談です。多くの市区町村では、ゴミ屋敷による生活環境の悪化や火災リスクを公的問題として受け付けています。環境課や地域生活課、防災担当に連絡すれば、現地調査や指導、最終的には過料(罰金)などの対応につながることもあります。たとえば豊田市では、条例に基づいて行政が強制撤去を行った事例もあります。
また、放火対策として警察に相談し、パトロールを依頼するのも効果的です。ゴミ屋敷周辺が暗く人目につきにくい環境であれば、不審者に狙われやすくなります。巡回を強化することで、「見られている場所」と印象づけ、放火の抑止力につながります。
さらに、自治会や町内会で情報を共有し、地域ぐるみで対策することも大切です。一人で対応するよりも、複数人で動いたほうが行政も動きやすくなります。また、ゴミ屋敷の住人が高齢や孤立している場合、福祉的な支援にもつながりやすくなります。
「まさか火事になるなんて」と後悔する前に、身近な小さな違和感に気づいたら行動する。それが自分や家族、地域の安全を守る第一歩です。
参考:豊田市|豊田市不良な生活環境を解消するための条例の概要
まとめ
ゴミ屋敷は放火されやすく、ひとたび火が出れば周囲の住宅にも深刻な被害を及ぼします。 実際に全国で延焼事例が報告されており、可燃物が多く人目につきにくい環境は放火リスクを高めます。 しかも、失火責任法により加害者に賠償責任が問えないケースも少なくありません。火災を防ぐには、当事者の早めの片付けと、自治体や地域との連携が欠かせません。
弊社では、無料でゴミ屋敷の清掃業者をご紹介しております。お問い合わせは以下のフォームよりお気軽にどうぞ!