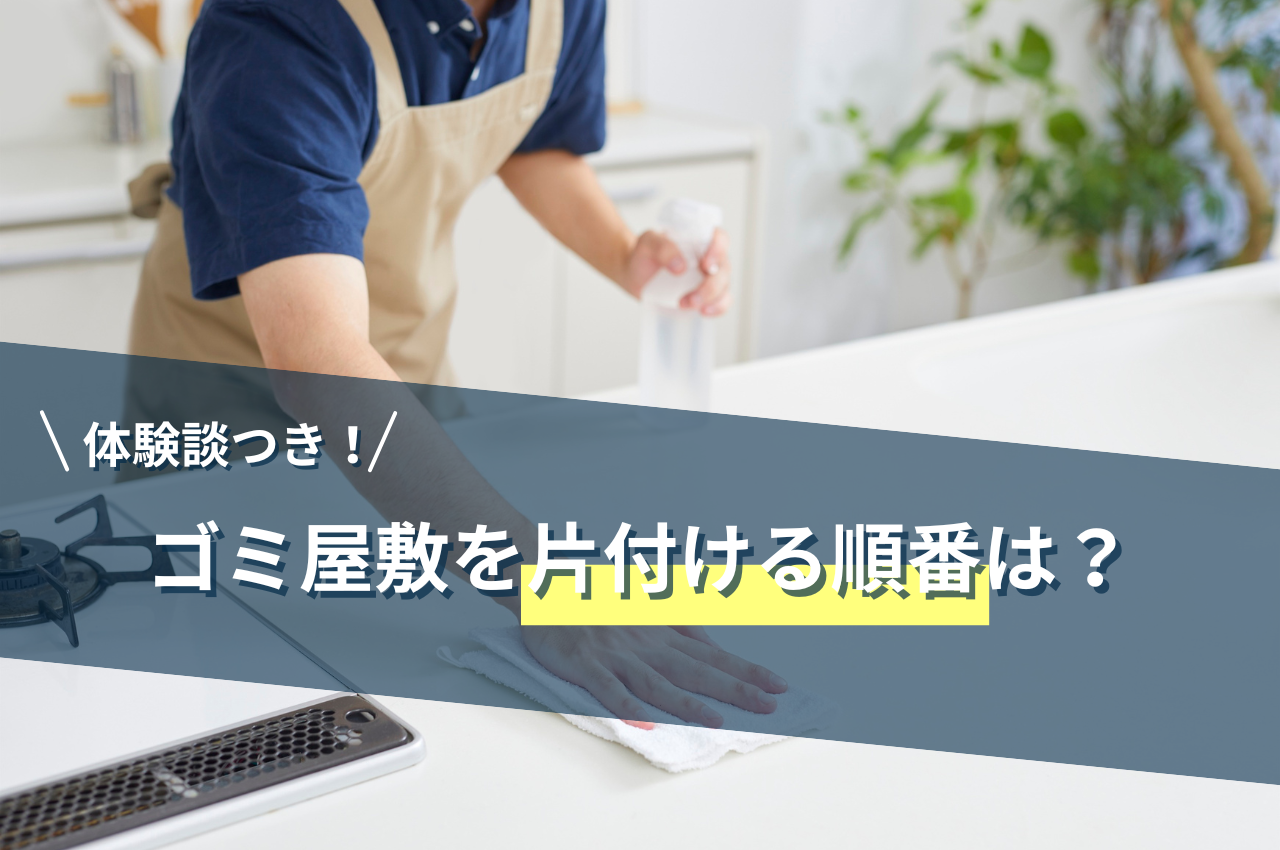ゴミ屋敷の原因はためこみ症?その背景と対策
投稿:
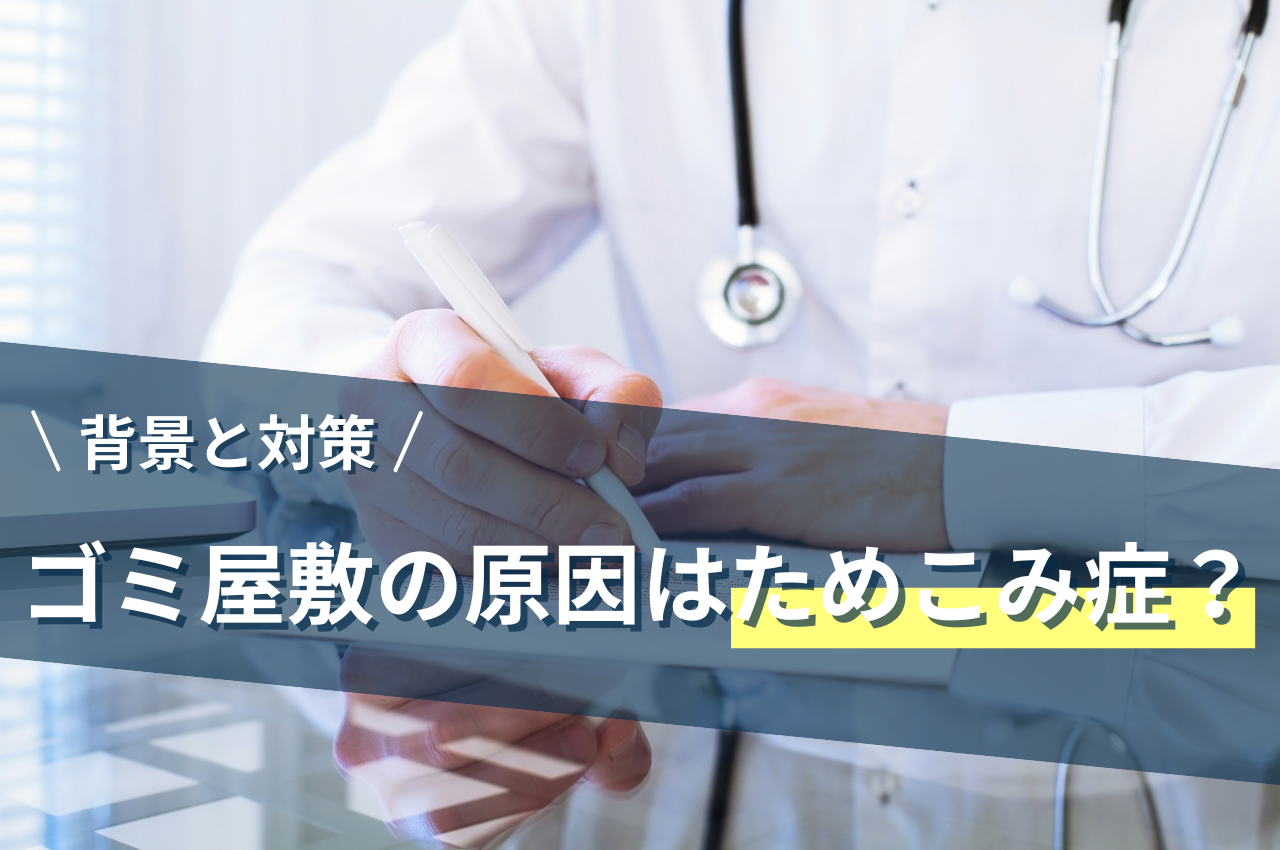
ゴミ屋敷。これは、家の中がゴミで溢れかえり、生活空間がほとんどない状態を指します。
おっと、このWEBサイトを見ている人なら説明不要ですね。
このゴミ屋敷という現象は、単なる片付けられない性格や怠惰によるものではなく、深刻な精神的な問題が背景にあることが多いというのです。
その一つが「ためこみ症(ホーディング障害)」です。
この記事では、ためこみ症がゴミ屋敷の原因となる背景や、その対策について詳しく解説していきたいと思います。
ためこみ症とは?
ためこみ症とは、不必要な物を捨てられないことで生活空間が物で埋め尽くされる精神障害です。主な症状としては、物を捨てることに強い抵抗を感じ、物に埋もれて生活が困難になることが挙げられます。
九州大学の偉い先生によるWEBページも見ておきましょう。
九州大学
ためこみ症の治療については、まだ標準化されたものはありませんが、認知行動療法の技法を利用した治療が、ある程度の有効性を示しています。私たちは、認知行動療法や薬物療法の可能性を探索するとともに、家族関係や生活環境の調整といった心理社会的背景へのアプローチも行いながら、ためこみ症治療にあたっています。
ためこみ症について – 九州大学大学院医学研究院精神病態医学 行動療法研究室

違います。素材集の人なんです。紛らわしくてごめんなさい
原因は性格や怠惰によるものではない
要するに、

捨てられんものばっかで勝手にゴミ屋敷になってまうねん。
という人がたくさんいるというわけです。
ためこみ症の診断と治療
ためこみ症の診断は、専門の精神科医、臨床心理士、またはカウンセラーなど専門家によるカウンセリングを通じて行われます。これには心理テストやインタビューが含まれます。
治療は認知行動療法や薬物療法が効果的だそうです。
認知行動療法(CBT)
ちんぷんかんぷんですね。
ためこみ症の患者さんというのは「これはいつか使うかもしれない」「捨てるのはもったいない」という自動思考があります。自動思考というのはその人が自然に考えてしまうこと、いわば『考えの癖』みたいなものです。
そこで。。。。
- 「本当にこれを使う可能性はどのくらいだろうか?」
- 「今まで一度も使わなかった物は何か?」
このような『こんな考えがあるよ』ということを指導します。
患者さんに「これを使う可能性は低いし、今捨てても問題ない。」ということを意識してもらい少しずつ物を整理し、捨てる練習をします。最初は使っていない古い雑誌や壊れた物から始め、徐々に他の物に取り組んでいきます。
患者さんは定期的にセラピストと会い、進捗を確認します。物を捨てることができた経験を共有し、成功体験を積み重ねていくんです。
まとめ
ゴミ屋敷の問題はゴミ屋敷の片付けをしたらオシマイではありません。その原因についても考える必要があるんです。個人だけでなく、社会全体で解決していくべき問題です。
ゴミ屋敷の問題の解決には、ためこみ症に関する理解を深め、周囲のサポートを呼びかけることが大事なんです。
ではまた。